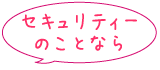施設警備業務の仕事内容は?依頼先はスタッフの質を要チェック!
施設警備員は商業施設をはじめ様々な場所で目にします。施設の安全な運営のために欠かせない施設警備ですが、業務を依頼する際はいくつかの注意点を確認しておくと安心です。こちらでは、施設警備の仕事内容や依頼のメリット、チェックしたいスタッフの質など、施設警備業務を依頼するうえで役立つ情報をご紹介します。大阪で施設警備の依頼をご検討の際は、ぜひご覧ください。
目次
施設警備業務として依頼できる内容とは?
施設警備業務として依頼できる仕事内容についてご紹介します。商業施設などで目にすることが多い施設警備員ですが、具体的な仕事内容はあまり知られていません。施設警備の仕事を長期で依頼をする場合、注意しておきたいポイントも存在します。施設警備の依頼でトラブルを防ぐために、仕事内容や長期依頼時の注意点などの情報が必要です。
施設警備員の主な業務内容

施設警備員の主な業務内容についてご紹介します。商業施設において警備の仕事を依頼したいと考えている方は、まず施設警備員がどのような仕事を請け負うのか、押さえる必要があります。主な業務内容について解説します。
受付業務
商業施設において欠かせない仕事の一つが受付業務です。施設警備員は施設の受付に常駐し、入館・退館する人を確認して不審者の侵入を防ぎます。また、商業施設は一般の利用者が使う出入口と、関係者専用の出入口が分かれているケースが多いです。関係者専用の出入口で受付対応を行い、関係者以外が利用しないように防ぐことも大切な役割です。
施設の巡回業務
施設の巡回業務も施設警備員に強く求められます。巡回業務といっても単に商業施設内を回るだけでなく、以下のような業務を行います。
- 窓やドアの確認、必要箇所が施錠されていなければ対応
- 防災機器などに異常がないかの点検
- トラブルがないかの見回り
なお、警備員が巡回しているという事実だけでも、商業施設利用者の安心感を高めるのに有用です。
トラブル発生時の対応
商業施設内でトラブルが発生したときは、施設警備員の迅速な対応が必要です。考えられるトラブル例を紹介します。
- 怪我人や急病人の発生
- 不審者や危険物の目撃情報
- 地震などの災害
- 施設機器関連のトラブル
このようなトラブルが発生した際に、施設利用者の安全を守ることも施設警備員の大切な仕事です。
商業施設などの施設警備を依頼したいと考えていても、どこに依頼するべきか、そもそもどのような警備会社が存在するのかは悩みやすい部分です。警備員の長期依頼でお悩みの際は、ケイ・ビー・エスまでご相談ください。大阪をはじめ、関西各地の警備業務を請け負います。商業施設だけでなく、各施設に求められる必要な警備業務をご提供します。長期依頼であっても対応可能です。予算や必要期間に応じてきめ細やかに設計します。
【施設警備業務】警備員と守衛の違い

警備員と似たイメージの職種として、守衛が挙げられます。警備員と守衛はどのように違うのか、施設警備ではどちらも依頼する必要があるのでしょうか。警備員と守衛の違い、両者の必要性について解説します。
法律が異なる
警備員と守衛のもっとも大きな違いは関係している法律です。警備員は「警備業法」という法律による規制を受け、従う必要があります。警備業法で定められている内容の例は以下のとおりです。
- 服装(規定に沿った制服の着用が必要)
- 警棒の形状や重量
- 欠格事由(警備員として勤務できない人の条件)
一方で守衛は警備業法の適用を受けないため、上記のような規定は存在しません。
雇用主の違い
警備員と守衛は雇用主が異なります。関連する法律が異なるのも雇用主の違いが理由です。警備員は商業施設などから依頼を受けて業務にあたる、いわば派遣の立場です。雇用主は施設関係者ではなく、所属する警備会社となります。依頼によって警備業務を行う場合は警備業法に従う必要があります。
対する守衛の雇用主は施設です。守衛は施設に所属する社員という立場であり、自社の保安警備を請け負うとされています。自社の社員が保安警備関連の業務を行う場合、警備業法の業務にはなりません。したがって、雇用主が施設である守衛は警備業法の規定に従う義務がないのです。
仕事内容に差はあるのか
警備員と守衛は法律や雇用主に違いがありますが、仕事内容自体には大きな違いはありません。どちらも施設の保安警備を行う立場であり、先述したような内容の仕事を実施します。警備員と守衛は施設の安全を維持するために必要な仕事です。細かな点に違いはあっても、実際に行う仕事に特別な相違点は見られません。しかし、法律や雇用主などで明確な違いは存在するため、同じ仕事と一括りにせず、両者の違いを押さえておくと安心です。
施設警備業務を依頼するメリットとは?
施設警備業務は警備員と守衛どちらでも対応できます。そのため、自社の社員を守衛として定め、警備会社へ依頼せずに保安警備を行うことも可能です。しかし、施設警備業務を外部に依頼することは様々なメリットがあります。施設警備員を配備する必要性、警備員の資格について把握しておくことで、施設警備業務を依頼するメリットの理解度を高めます。
施設警備員を配備する必要性

商業施設などにおいて、大きなトラブルが発生する事態は非常にまれです。そのため、施設警備員の配備はコストパフォーマンスが悪いと考えてしまうケースも起こり得ます。しかし、施設警備員の配備は重要な意味を持ちます。
警備員の姿そのものが犯罪の抑止力となる
施設警備員の姿は、見えるだけで犯罪の抑止力が期待できます。いるだけですべての犯罪が消えるわけではありませんが、警備員がいるか否かは犯罪率に大きな影響を与えます。また、施設警備員の姿は利用者へ安心感を与えるという効果も大きいです。施設警備員の姿が見えることで、防犯・安全に配慮している施設という印象を与えられます。利用者の安心感は施設への信頼につながるため、非常に重要なポイントです。
施設警備員が行う業務は様々
施設警備員の業務は一見すると地味というのは事実でしょう。大きなトラブルが起こらない限り、ドラマのような施設警備員の活躍を実感できる場面がないという点も存在します。しかし、施設警備員は施設の安全を守るため、非常に多くの業務を行っています。主な仕事内容として受付や巡回業務、トラブルの対応業務があり、各業務の中にはさらに細かい業務が多数存在します。
もし施設警備員が配備されていなければ、このような細かい業務を別の人が実施する必要があります。前述した守衛についても、必要な人員を自社のみで確保するとかなりのコストや時間がかかります。必要な業務を実施させるために自社内で教育、管理も必要です。これらを自社のみで対応するのは煩雑なため、外部に依頼したほうが効率的なケースが多いです。
【施設警備業務】スタッフの質が違う!警備員の資格

警備員は警備業法の欠格事由に該当せず、必要な研修を受けると業務可能です。しかし、警備員に関する資格保有者は一定以上のスキルや知識を持ち、質の高さも保証されています。警備業務を依頼する際は、資格の有無を確認してみるのもポイントです。
施設警備業務検定とは?
施設警備業務検定は、施設警備に関する知識やスキルを問われる検定試験です。学科試験と実務試験の両方から構成されており、座学による知識だけでなく、実務能力も測れます。試験で問われる内容は以下のとおりです。
- 警備業務の基礎的事項
- 警備と関連する法令
- 施設の保安に関連する知識
- トラブル発生時の措置方法
一般的な研修でも最低限必要な知識を身につけられますが、検定の合格者はより高レベルな知識・スキルを身につけています。したがって高い質が期待できます。
施設警備業務検定の概要
施設警備業務検定は2級・1級がありますが、試験の形式や合格基準点は同じです。20問の学科試験と6科目の実務検定から成り立ちます。学科試験・実務試験いずれも90点以上を取得した場合が合格です。
2級であっても講習を受講せずに検定試験を受けた場合、合格率は4割程度と半分にも届かず、講習を受けても2割〜4割は不合格となってしまう試験です。より難易度の上がる1級は、さらに合格率が下がります。その分、施設警備業務検定に合格した警備員は高い質を持つため、安心して業務を任せられます。資格の有無は警備員の質を保証する目安となり、業務を依頼するにあたって有用なポイントです。
大阪を中心に警備サービスを提供するケイ・ビー・エスにも、資格保有者が多数在籍しています。お気軽にご相談ください。
施設警備業務の理解が安心・安全な施設につながる!
施設警備業務について理解を深めることで、適切な警備員配備が可能となり、結果として安心・安全な施設につながります。なかなか重要性がわかりにくい業務かもしれませんが、円滑な施設運営のために重要な役割を担う存在です。施設警備員の重要性について実感いただけるきっかけになれば幸いです。
ケイ・ビー・エスでは施設警備をはじめ、様々な警備業務を請け負います。資格保有者も多数在籍しているため、質の高い警備業務が可能です。大阪周辺で警備業務の依頼を検討している方は、ぜひご相談ください。
警備の役割や費用に関するコラム
大阪周辺で施設警備業務のご依頼はケイ・ビー・エスへ
| 社名 | (有)ケイ・ビー・エス |
|---|---|
| 所在地 | 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目17番5号 1146号 |
| tel | 06-6160-4565 |
| URL | https://k-b-s.info/ |